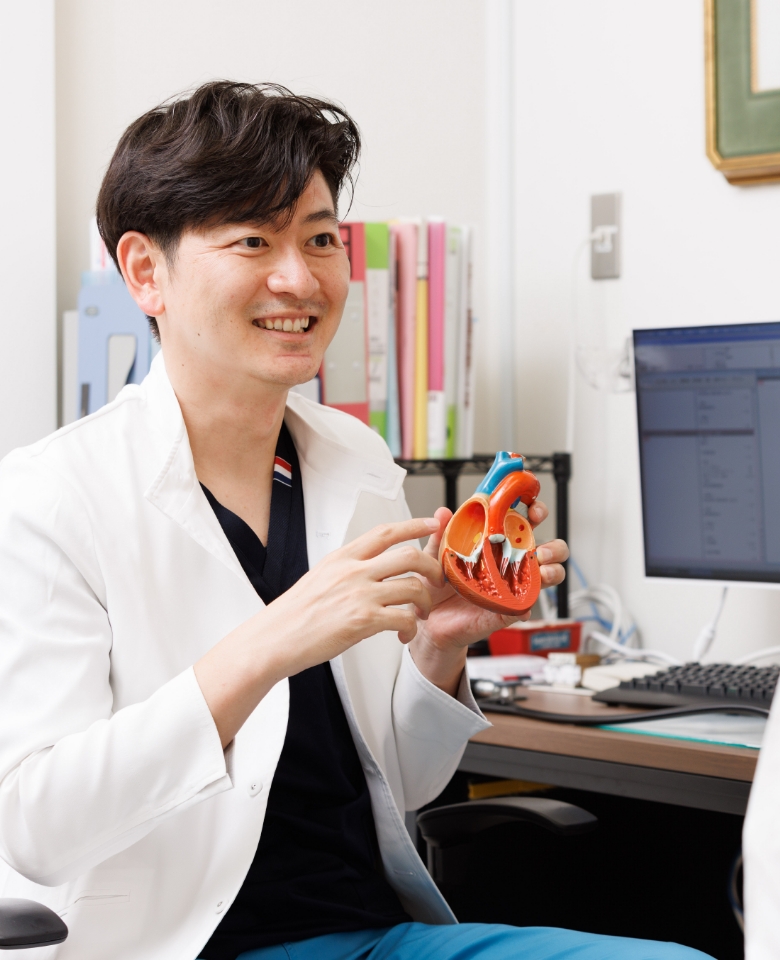3月が近づき、寒さの中にも暖かい日差しが感じられるようになってきました。東大友内科の待合室に鳥の彫り物があるのをご存じだと思います。長年通院されている患者様のご厚意でお借りしています。自動血圧計の横に置いてありますので、すばらしい作品を是非ご鑑賞ください。今回も珍しい鳥をお貸しいただきました。真っ赤なカワセミ”アカショウビン”です。カワセミ科は春から夏にかけて渡来する渡り鳥で、青色のカワセミはクリニック裏の用水路でも身近に見ることができるとの言です(残念ながら私はまだ遭遇できたことはありません)。ただカワセミをはじめ渡り鳥ですが、飛来する時期や場所が徐々に変わっているようで気候変動などの影響では?と今後を危惧されていました。
我々人間も気候変動は大きく影響しており、自律神経の不調で来院される方も多くなっています。特に睡眠障害は季節の変わり目に多く、体調不良に大きく関わります。また不眠が起きると更に様々な自律神経障害を及ぼす可能性も高く、ついには精神疾患の発症にも繋がるとされています。最近のデータでは、成人の30%が不眠症状(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠困難)を有し、6〜10%が不眠症を罹患しているようです。50歳以上の中高年層では不眠が原因でうつ病や生活習慣病の罹患率が増加するとされ、不眠による生活の質(QOL)の障害が長期欠勤や生産性の低下、産業事故の増加など公衆衛生学上でも大きな社会問題となっており、正に現代病の1つと言えます(※)。睡眠薬の処方については諸説あり、早期に介入するかはそれぞれの患者様の状況に合わせてになりますが、日々の生活で不眠を改善できる可能性もあります。携帯はじめブルーライトとメラトニンの関係は有名ですが、入眠禁止ゾーン(sleep prohibitied zone)があることご存じでしょうか?我々は睡眠欲求と起きていようとする覚醒シグナルがさまざまな環境でお互いバランスを取りながら機能しています。睡眠欲求は日中の疲労蓄積の結果として起きている時間に比例して増大しますが、逆に覚醒シグナルの強度は拮抗する形(眠くならないように働く形)で、時刻依存性に増加します。とくに入眠の2〜3時間前の時間帯は覚醒シグナルが最も高くなるために入眠(睡眠)禁止ゾーンとも呼ばれています。入眠禁止ゾーンは寝たくても寝れない時間帯との解釈もあるようですが、夜勤などで睡眠時間帯が大きく変わる人にはこの時間帯で寝れないと睡眠時間が短くなり死活問題となります。入眠禁止ゾーンの改善方法も色々ありますが、深部体温の低下で入眠を促す方法は比較的簡単に日々の生活に取り入れることができます。ぬるま湯に長く浸かったり、ヨガを行うなどで深部体温を高めておき、徐々に体温を低下させることで睡眠を促す方法です。季節の変わり目の不眠などは薬剤を使用せずに乗り切れることも多いので、特になかなか寝れないなど入眠障害の方は是非一度お試し下さい。もちろん東大友内科では自律神経障害や不眠症の加療や薬を使わないアドバイスなどもさせていただきます。ご心配な際はご相談ください。
※参考資料;睡眠薬の適正使用・休薬ガイドライン

診察室にもたまにカワセミが飛来します。