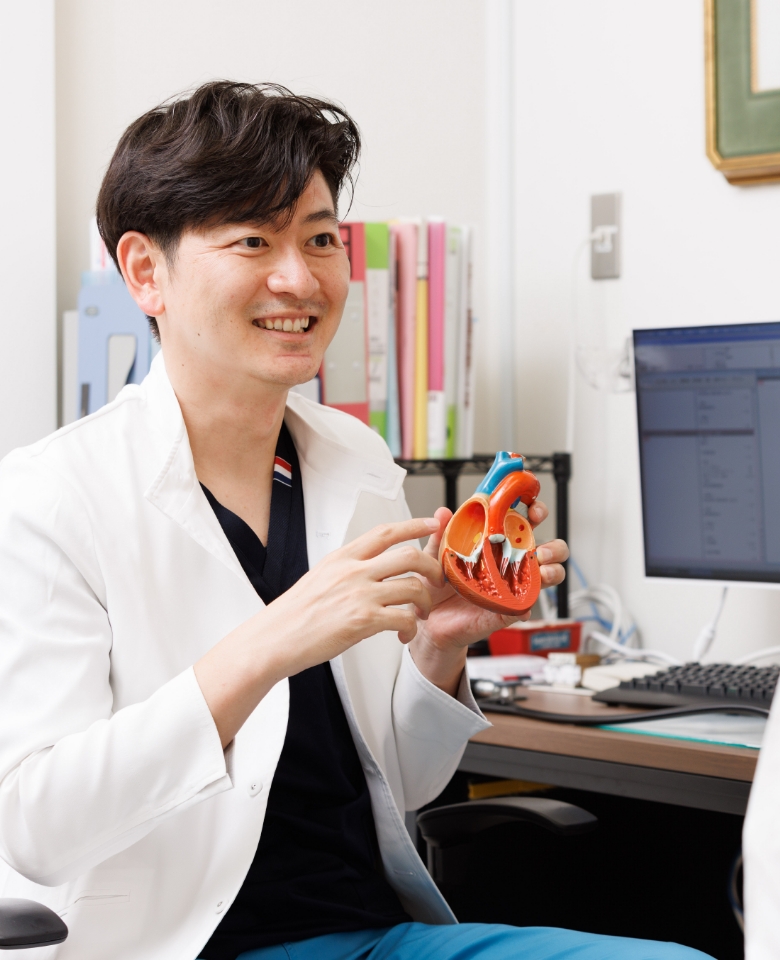桜が咲き新年度がスタートしました。ご体調はいかがでしょうか。今日は外来で患者様に良く相談されるビタミンDについて書こうと思います。
桜が咲き新年度がスタートしました。ご体調はいかがでしょうか。今日は外来で患者様に良く相談されるビタミンDについて書こうと思います。
ビタミンDは骨を強くして骨折の予防に繋がる事が知られていますが、最近では骨以外の作用についても研究が進んでいます。代表的なものとしては、がんの発症予防や免疫力の活性化、筋肉の増強を促して転倒予防の効果がある等です。
そんな素晴らしい効能が期待されるビタミンDですが世界的にみて摂取不足が懸念されており、日本では厚生労働省が高齢者の栄養不足やフレイル(虚弱体質)防止の目的からビタミンDの摂取基準を8.5㎍/日に引き上げています。対して脂溶性ビタミンである事から大量の摂取は身体に蓄積してしまい不調の原因になるため注意が必要です。
ビタミンDは、ビタミンD2(多くは植物由来)とビタミンD3(多くは動物由来)の総称で、キノコ類や魚で摂取できます。なお一般的にビタミンD2に比べビタミンD3の方が生理活性が強いとされていますが、骨を強くするにはビタミンDの他にマグネシウムが必要で、キクラゲはどちらの成分も豊富に含まれておりとても注目されている食品でオススメです。魚であればさんまや鮭がビタミンDが豊富です。
なお体内に入ると肝臓、腎臓で代謝されて活性型ビタミンDになり初めて体内で有効なものになりますがその際に「日光を浴びる」事が必要です。
しかし日光(特に紫外線)は浴びすぎるとシワやシミ、皮膚病の原因になってしまうので浴び方を工夫をしましょう。国立環境研究所地球環境研究センターのサイトでは、「特に皮膚が炎症を起こす最少の時間を示し、それ以上の日光照射は避けたほうが良い」という目安が公開されおり、具体的に「今日の日差しならどれだけ日光を浴びても良いか」をリアルタイムで確認出来ます。なお個人差はありますが、その時間は概ね夏は10分、冬は20分程度とされています。
詳細は下記HPをご参照ください。
https://db.cger.nies.go.jp/dataset/uv_vitaminD/ja/mobile/kaisetsu.html
またすでに活性型ビタミンDになっているビタミンを摂取する方法もありますが、活性型ビタミンDは病院で処方する内服薬しかありません。
足腰を鍛え骨を強くするためにも、自分のペースで結構です。ビタミンDをしっかり摂って外でウォーキング始めましょう。
参考文献、参考サイト
Emily, M. J Periodont Res. 2023;58:213–224.
Annweiler C,Souberbielle JC.J Nutr Health Aging .2023;27(8):607-608.
厚生労働省 eヘルスケアネットサイト
国立環境研究所地球環境研究センターのサイト
https://db.cger.nies.go.jp/dataset/uv_vitaminD/ja/mobile/kaisetsu.html